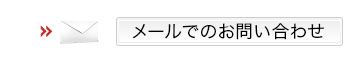権利の窓
2007年08月16日 民法入門35 「時を遡る制度」
時効 総則 時効の遡及効 ―民法入門35―
「時を遡る制度」
前回の「時効考察」に続き筆を執らせていただきます。ところで、筆者はこの「権利の窓」のタイトルを、何らかの元ネタをもじったりして付けています。前回のタイトルは「時効○察」という某ドラマ名をいただいてきたのですが、普通に妥当なタイトルになってしまったお陰で気づいた方はいらっしゃらなかったでしょう。今回も何だかそのまんま過ぎて、少し自己嫌悪です。
さて、そんな与太話で行数を稼がずに今回のお題に入りましょう。今回は時効の遡及効。遡及効とは読んで字の如し、「遡って及ぼす効力」です。民法144条には「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」とあります。前回簡単にお話しした、取得時効や消滅時効の効力は、時効の期間が経過したその時から発生するのではなく、期間の起算日にさかのぼってその効力を発生させる、と言っているのです。
この遡及効がもし無い場合、仮に一定期間頑張って土地を占有していた者が、晴れてその土地を時効取得したとして、その取得の効力が一定期間経過時(時効の完成と言ったりします)に発生するとされた場合、時効取得者は、時効の完成時以降は真の所有者と言えるかもしれませんが、時効が完成するまでは単なる不法占拠者なわけですから、時効完成によって自らの所有権を失うことになる元の所有者から、時効が完成するまでの不法占有による損害を賠償しろ、などと言われかねません。
また、占有している間に元の所有者がこの土地を借金の担保として抵当に入れた場合、時効取得者はたとえ真の所有者となったとしても、いつ元の所有者の借金のカタにこの土地が取られるかに怯えなければならなくなります。こうした不都合があっては、せっかく強力な効力を発生させる時効制度が骨抜きになってしまいます。この問題を遡及効は見事にクリアしているのです。
遡及効により前述の時効取得者が、当該土地の占有初日から所有者であったとみなされた場合、当然不法占拠者でもないですし、占有開始後に元の所有者が土地を抵当に入れようと、遡及効のためにその効力は否定され、時効取得者は何ら怯える必要もありません。早い話、時効取得者は占有開始時における当該土地の状態のまま、その所有権を取得しするのです。これを「原始取得」と言ったりします。
次に消滅時効と遡及効に関してのお話しに移りましょう。消滅時効とは一定期間の経過により権利を消滅させる制度です。この効力も起算日にさかのぼって発生します。この起算日は「権利を行使することができる日」と言い換えることができるのですが、この権利を行使することができる日というのが、権利の種類によってまちまちで、ややこしいのです。ですから消滅時効の例示に最もよく使われる権利である債権、しかも金銭債権を使用して「権利を行使することのできる日」のイメージを掴んでいただきましょう。
例えば貸した金を返してくれとも何とも言わずに一定期間(通常10年ですが例外多数)経過すると、その金銭債権は消滅してしまうのですが、その消滅の効力は、上記の例であれば、「金を返してくれと言えるようになった日」に消滅したものとされてしまうのです。この「金を返してくれと言えるようになった日」も返済期限を決めてある貸金であればその期限の到来時である、と簡単にわかるのですが、知人間の貸し借りなど、いちいち返済期限を定めない債権もあるでしょう。この場合、金を貸したその時から、返してくれと言うことが法律上可能ですから、金を貸し日たから一定期間何らのアクションを起こすこともなく経過すれば、金を貸したその日に債権が消滅したものとみなされます。これらの例で、債務者が金を返さなくても良くなるのは、一定期間経過した時です。金を返さなくても良くなるのですから、わざわざ遡及効など認めなくてもいいような気もしますが、遡及効がないと、債権そのものが消えても、それに付帯する利息や遅延損害金が消えないことになってしまいます。消滅時効は「権利を行使できるにも関わらず行使しない場合、権利を行使できる初日に行使があり、履行により消滅していたものと考える方が自然である」という考え方に基いていますから、利息や損害金だけ残ってはこの考え方を全うできません。
時効は、ある事実状態が長く続く場合、真実がどうであれ、その事実状態を重視し、事実状態全体に意味を持たせ、結果として権利の取得や消滅を発生させる制度です。遡及効はその効力と事実状態の間の辻褄を合わせるため、必要不可欠なものと言えるでしょう。
(作成者 佐野 晋一)